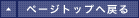2011年4月6日 豊島 維
1 はじめに
東日本大震災によって損傷を受けた福島第一原子力発電所(以下「第一原発」)の問題は、長期化するばかりでなく日を追うごとに深刻さの度合いを増し、被害が広がっている。そして、その補償の問題に関し、原子力損害の賠償に関する法律(以下「原賠法」)の内容、それが今回の事象に適用されるか、適用があるとして、どの範囲の損害についてどのような救済が与えられるのかという問題に大きな関心が集まっている。しかし、東日本大震災自体が未曽有の事象であり、原賠法の制定過程においても、原賠法の運用をめぐるこれまでの議論においても、今回のような事態は想定されてこなかったという事情があり、原賠法の解釈、適用の問題はそう単純ではない。そこで、以下においては、原賠法の概要をかいつまんで紹介したうえ、問題点の整理、検討を試みたい。
2 原賠法の概要
(1)原賠法の趣旨・基本構造
日本で初の原子力発電が行われたのは昭和38年(1963年)であったが、その前々年の昭和36年(1961年)に原賠法が制定された。この法律は、原子力の実用化へ向け、原子力事故が起こった場合の被害者の救済等を目的として制定されたものである。原賠法のもとでは、原子炉の運転等【注1】により原子力損害【注2】が発生した場合には、原則として第一義的に原子力事業者【注3】が原子力損害の被害者に対する無限の損害賠償義務を負う(原賠法3条1項本文)。この場合、原子力事業者はあらかじめ義務づけられている損害賠償措置【注4】に基づき、損害賠償措置額までは保険会社又は政府から金銭の提供を受けこれを被害者への賠償に充てることができるが、損害賠償措置額を超える損害が生じた場合には、これを超える部分について損害賠償義務を免れない。その結果、損害が原子力事業者の支払能力を超える可能性も存在することから、被害者の救済のために、損害賠償措置額を超える部分については政府が原子力事業者に対して必要な援助を行うこととされている(同16条)。また、例外的に「異常に巨大な天災地変又は社会的動乱」によって原子力損害が生じた場合には、原子力事業者は免責されるが、その代わりに政府が被害者保護のために必要な措置を講じることになる(同3条1項ただし書、同17条)。
(2)原賠法の責任と民法の不法行為責任との関係
被害者が加害者に損害賠償を求める根拠・方法としては、民法上の不法行為責任を追及するのが原則であり、原賠法は、この点民法の不法行為責任の特則である。民法上の不法行為責任を追及する場合、加害者に故意・過失があることが必要であり、また、故意・過失の存在については被害者の側でこれを立証しなければならないが、原賠法のもとでは、原子力事業者は故意・過失の有無を問わずに被害者に対する損害賠償責任を負うことになる。そのため、被害者が原子力事業者に対して原賠法の責任を追及する場合、原子力事業者の故意・過失を立証する必要はなく、仮に原子力事業者が無過失であっても損害賠償責任を免れないという点で、民法によるよりも責任追及が容易である。
これに対し、原子力事業者以外の者(原子炉の設計者や機器の製造業者等)に対する責任追及については、原賠法上は原子力事業者に責任が集中しており、原子力事業者以外の者は損害賠償責任を負わないこととされている(原賠法4条1項)。この場合に、原子力損害の被害者が原子力事業者以外の者に対して民法の不法行為責任を追及することができるかどうかについては、原賠法4条1項が原子力事業者以外の者が責任を負わないことを明記していることから、被害者は、原子力事業者以外の者に対しては、原賠法上はもちろんのこと民法を含むその他のいかなる法令によっても損害賠償を請求することはできないと判示した裁判例がある【注5】。ただし、原子力事業者以外の者の責任を原子力事業者自らが追及できるかどうかは別問題である。
3 賠償の対象となる「原子力損害」の範囲
原賠法により賠償されるべき「原子力損害」の範囲については、原賠法に特則が存在しないため、民法の一般原則に従って、原子炉の運転等と相当因果関係がある損害はすべて含まれると解されている【注6】。すなわち、被害者の死亡、人身傷害、財産の滅失又は毀損という直接損害に限らず、休業損害、待避命令による退避損失、慰謝料【注7】等の「間接損害」も、相当因果関係が認められる範囲内であれば「原子力損害」に含まれることなる。
また、風評被害による商品の売上減少についても、仮に当該商品について放射能汚染等の影響が生じていなくとも、原子力事故及びその報道によって風評被害が生じ、消費者が商品を買い控えた結果売上が減少するなど、原子炉の運転等と売上減少との間に相当因果関係があると認められれば「原子力損害」と認められることになる【注8】。
しかし、これらの被害が「原子力損害」と認められるためには、被害と原子炉の運転等との間に相当因果関係があることが要件となるため、健康被害が生じた場合にそれが放射線の作用等によって生じたといえるかどうかや、過度に遠方に避難したり高額な宿泊施設に宿泊したりした場合の避難費用がどこまで相当因果関係の範囲内に含まれるといえるのかなど、損害の認定・損害額の算定には困難がつきまとう。
特に、風評被害による売上減少については、一般に売上の減少には様々な要因が考えられるため、どの範囲までの売上減少について相当因果関係のある「原子力損害」として認められるのかという判断が極めて難しい。そのため、JCO臨界事故【注9】の際に設置された原子力損害調査委員会や裁判例では、損害の範囲に場所的・時間的しばりを設ける考え方が提示されている【注10】。
4 東京電力株式会社の免責の有無-「異常に巨大な天災地変」
原子力損害の被害者が原子力事業者に損害賠償を請求しようとする場合、原子力損害が「異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によって生じたものであるとき」には原子力事業者は免責されるため、原子力事業者の免責の有無のメルクマールになる「異常に巨大な天災地変」の意義が問題となる。この点、国会の委員会等における原賠法の立法・改正の審議過程によれば、「異常に巨大な天災地変」とは俗に言う不可抗力よりも範囲の狭い「超不可抗力」、「ほとんど発生しないような、考えられないような事態」、「日本の歴史上余り例の見られない大地震、大噴火、大風災等」であり【注11】、地震に関していえば、これまでに起こった日本における最大の地震に耐え得ることを前提に、例えば関東大震災と同等程度及びその2~3倍程度の地震は「異常に巨大」には当たらないと考えられているようである【注12】。しかし、具体的にどの程度の地震があった場合に「異常に巨大」といえるのかどうかということについては、それ以上に明確な基準付けがなされた形跡は伺えない。
東日本大震災については、気象庁の発表による地震のマグニチュードは9.0であり、地震の規模としては関東大震災の7.9を上回る日本国内観測史上最大を記録し、アメリカ地質調査所によれば、1900年以降世界でも4番目の規模と発表されている。関東大震災との比較でいえば、東日本大震災の地震エネルギーは関東大震災の約45倍とも言われている。また、この地震によって発生した津波は国内最大級の津波(東京大学地震研究所の調査では標高37.9メートル)であると指摘され、第一原発を襲った津波の高さは14メートル以上であったと報道されている。このような地震や津波の規模からすれば、東日本大震災が「異常に巨大な天災地変」に該当し、原子力事業者である東京電力株式会社(以下「東京電力」)は免責されるとの解釈も成り立ち得る。しかし、その一方で、原賠法は被害者の保護を主たる目的として制定された法律であること、同法の制定過程においても、原子炉ではひとたび事故が起これば大災害が生じるおそれがあることから、これまでの経験から予想し得るものはすべて予想して万全の措置(地震でいえばこれまでに日本で起こった最大の地震に耐え得るものであることはもちろん、さらに余裕をみた原子炉の設計その他の措置)を講じることが要請されるといった説明がなされていること【注13】、第一原発については、平成21年に経済産業省の専門家会合において大津波を考慮すべきであるとする意見がなされたり【注14】、同型の原子炉の設計にもろさがあったとの指摘が報道されたりしていることを考慮すれば反対の結論になることも考えられる。
この点について、昨日来の報道によれば、政府の指示を受けて東京電力が原賠法に基づく損害賠償について仮払金を支払う方向で調整に入ったとの報道もなされており、もしこれが事実であれば、東京電力の側で「異常に巨大な天災地変」の意義を積極的に争わず自社の損害賠償責任を認めるということになるであろうから、この問題には決着がついたといえる。
なお、震災後の東京電力の初期対応が適切であったかどうかの詳細は今後の調査を待つことになるが、仮に震災後の東京電力の作為・不作為によって損害が拡大し、その作為・不作為が同社の過失によることが明らかになった場合の東京電力の責任については、なお検討すべき問題がある。地震が「異常に巨大な天災地変」に該当しない場合には、東京電力が被害者に対して第一義的な責任を負っていることから、この問題は一連の事故と損害の発生との間の相当因果関係の問題に解消されると考えられる。他方、地震が「異常に巨大な天災地変」に該当する場合には、本来免責されるはずの東京電力の震災後の作為・不作為によって損害が拡大したことについて、「原子炉の運転等」以外の東京電電力の作為・不作為によって損害が生じたとして民法上の不法行為責任を負わせることができるのか、またその場合にどこまでの損害について責任を負わせることができるのかということについて、判断の困難な問題が生じる。
5 損害賠償措置額を超える損害が発生した場合の取り扱いとその問題点
東日本大震災が「異常に巨大な天災地変」に該当しない場合には、第一義的には東京電力が被害者に対する無限の損害賠償義務を負うことになる。この場合にまず被害者の損害賠償に充てられる原資は原子力損害賠償補償契約に基づいて政府から補償される補償金であり、補償金を超える原子力損害については東京電力が被害者にこれを賠償する責任を負う。しかし、補償金を超える損害賠償金が多額に及び東京電力の支払能力を超えるような場合には、被害者の救済のために、政府が東京電力に対して必要な援助を行うこととなる。
これに対し、東日本大震災が「異常に巨大な天災地変」に該当する場合には、東京電力は免責されるため原子力損害を被った被害者に対して原賠法上の損害賠償責任を負うことはないが、その代わりに政府が被害者保護のために必要な措置を講じることとなる。
しかし、政府の「援助」についても「措置」についても、援助や措置がどの範囲で講じられるのかということは原賠法上明記されていないほか、援助や措置を講じることが法律上の義務として規定されているわけでもない【注15】。また、政府は国会の議決によって政府に属させられた権限の範囲内で援助や措置を行うこととされているため(原賠法16条、17条)、援助や措置を実行するためには国会の議決が必要となる。
このような被害者保護の体制に関する懸念は原賠法の制定当時から指摘されてきたところであり【注16】、原賠法上は、損害賠償措置額を超える損害が発生した場合、その超える部分の損害が完全に賠償・補償されるかどうかについては不透明・不確実な部分が残っている。
6 おわりに
このように原賠法には様々な論点があるほか解釈の分かれる部分や不明確な部分もあり、司法手続に乗せると結論が出るまでに気の遠くなるような年月を要すると思われる。また、第一原発からの放射性物質の漏出はいまだ収束しておらずその見通しもたっていないのに対し、第一原発の周辺の農業・畜産業は出荷停止という甚大な痛手を受け、避難指示を受け避難した人々の帰宅の目処も立っていない。これらの人々の損害は日々増大していく一方であり、既に検討が始まっている仮払金の支払いをはじめ、簡易迅速な救済を与えるための特別な措置が望ましい【注17】。また、賠償されるべき損害の範囲についても、被害者の迅速な救済と不公平感をなくすため、原子力損害賠償紛争審査会(原賠法18条)による統一的な指針ができるだけ早急に策定されることが望まれる【注18】。他方、各地で訴訟が多発することも予想されるが、その場合には迅速かつ適切な処理が可能となるよう、何らかの手続的な手当ても必要となろう。
以上
*****************************************************************************
【注1】「原子炉の運転等」とは原子炉の運転、加工、再処理、核燃料物質の使用、使用済燃料の貯蔵、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄及びこれらに付随してする核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の運搬、貯蔵又は廃棄であって、政令で定めるものをいう(原賠法2条1項)。
【注2】「原子力損害」とは、核燃料物質の原子核分裂の過程の作用又は核燃料物質等の放射線の作用若しくは毒性的作用(これらを摂取し、又は吸入することにより人体に中毒及びその続発症を及ぼすものをいう。)により生じた損害のうち、損害賠償の責任を負う原子力事業者が受けた損害を除いたものをいう(原賠法2条2項)。
【注3】「原子力事業者」とは、原子炉の設置許可を受けた者、核燃料物質の加工の事業の許可を受けた者、使用済燃料の貯蔵の事業の許可を受けたもの、使用済燃料の再処理の事業の指定を受けた者、核燃料物質または核燃料物質によって汚染された物の廃棄の事業の許可を受けた者、核燃料物質の使用の許可を受けた者等をいう(原賠法2条3項)。具体的には、電力会社である東京電力株式会社や日本原子力発電株式会社、電源開発株式会社等のほか、大学等における研究用の原子炉の設置者も原子力事業者に該当することになる。
【注4】損害賠償措置の内容は、原子力損害賠償責任保険契約及び原子力損害賠償補償契約の締結若しくは供託である。原子力損害賠償責任保険契約は原子力事業者と民間の保険会社との契約によりなされるものであり、一般的な事故による原子力損害をカバーする。原子力損害賠償補償契約は原子力事業者と政府との保証契約であり、原子力損害賠償責任保険で補填されないケース(地震、噴火、津波によって生じた原子力損害、正常運転によって生じた原子力損害、原子力事故等があった時点から10年を超えてから損害賠償請求がなされた場合)をカバーする。賠償措置額の上限は、いずれも1工場若しくは1事業所若しくは1原子力船あたり1200億円である(原賠法7条1項)。
【注5】水戸地判平20.2.27・判タ1285号201頁、東京高判平21.5.14・判時2066号54頁。なお、原子力事業者に対して民法の不法行為責任を追及することの可否についても、賠償されるべき「原子力損害」の範囲に関して民法と同様に解するのであれば、原子力事業者に原子炉の運転等以外の責任を追及するような場合でない限り、原賠法以外に別途民法上の責任を認める意義はないと思われる(東京地判平16.9.27・判タ1195号263頁)。
【注6】第38回国会参議院商工委員会会議録第26号(昭36.5.26)、第38回国会参議院商工委員会会議録第27号(昭36.5.30)、竹内昭夫「原子力損害二法の概要」ジュリ・236号31頁。
【注7】この点について、原子力損害調査研究会最終報告書(平12.3.29)では、身体傷害を伴わない精神的苦痛のみを理由とする請求については特段の事情がない限り損害とは認められないとの見解が示されているが、東京地判平18.4.19・判時1960号64頁は身体傷害を伴わない損害についても慰謝料を認めている。
【注8】名古屋高判平元.5.17・判タ705号108頁、東京地判平18.2.27・判タ1207号116頁、前掲東京地判平18.4.19
【注9】平成11年9月30日に茨城県東海村にある株式会社ジェー・シー・オー(JCO)東海事業所の「転換試験棟」で発生した国内初の臨界事故。
【注10】原子力損害調査研究会最終報告書(平12.3.29)、敦賀湾に放射性物質が漏出した原子力事故について、金沢産の魚の売上減少と事故との相当因果関係を否定した裁判例として前掲名古屋高判平元.5.17、JCO臨海事故について、事故と茨城産の納豆の売上減少との相当因果関係を認めながらも、時間的制限(それぞれ事故発生から2か月、5か月)を設けた裁判例として前掲東京地判平18.2.27、前掲東京地判平18.4.19。
【注11】第38回国会衆議院科学技術振興対策特別委員会議録第14号(昭36.4.26)、第38回国会参議院商工委員会会議録第26号(昭36.5.26)、第87回国会参議院科学技術振興対策特別委員会会議録第13号(昭54.6.1)、第3回原子力損害賠償制度専門部会配付資料(平成10年9月11日)
【注12】第38回国会衆議院科学技術振興対策特別委員会議録第9号(昭36.4.12)、第38回国会参議院商工委員会会議録第25号(昭36.5.23)、第38回国会参議院商工委員会会議録第27号(昭36.5.30)、第3回原子力損害賠償制度専門部会配付資料(平成10年9月11日開催)
【注13】第38回国会参議院商工委員会会議録第27号(昭36.5.30)
【注14】経済産業省総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会 耐震・構造設計小委員会 地震・津波、地質・地盤 合同WG(第32回)(平21.6.24)、同(第33回)(平21.7.13)
【注15】ただし、政府関係者は国会での答弁で、援助や措置を「行うものとする」、「講ずるようにするものとする」という規定は、「行うことができる」とか「行うよう努める」といった規定ではないため、政府に強い責務を付与する規定であり、必要な対応措置が必ずとられることになるとの考えを述べている(第145回国会衆議院科学技術委員会議録第5号(平11.3.16)、第171回国会参議院文教科学委員会会議録第7号(平21.4.9))。
【注16】第38回国会衆議院科学技術振興対策特別委員会議録第14号(昭36.4.26)、第38回国会参議院商工委員会会議録第26号(昭36.5.26)、第171回国会衆議院文部科学委員会議録第5号(平21.4.1)
【注17】平成11年9月30日に発生したJCO臨界事故の際には、被害を受けた村商工会が中心となって結成された「JCO臨界事故損害賠償対策協議会」らの強い働きかけを受けて、原子力事業者であるJCOが、国・茨城県・東海村とも協議のうえ、平成11年12月中に、健康被害に係る経費は全額、その他の損害については請求額の2分の1について仮払いを行った。また、仮払いに際しては東海村や茨城県の職員が交渉の窓口となった。その後、JCOは年明けから被害者との間で賠償金の確定交渉を開始し、平成12年3月末までに約6000件の和解が成立した。他方、和解がまとまらずに裁判上の請求に至った案件も11件あった。
【注18】JCO臨海事故の際には、当初は原子力事業者であるJCOが「JOCの補償等の考え方と基準」を示したものの、加害者側からの一方的な賠償基準の提示は被害者側の反発を招き、被害者との補償交渉が難航した。そのため、当時の科学技術庁の委託により弁護士などの専門家から構成される原子力損害調査委員会が設置され、同委員会の発表した最終報告書において損害の考え方に関する見解が示されることとなった。