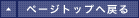2011年2月16日 田中 利彦
1 はじめに
今年1月31日、元民主党代表の小沢一郎氏が東京地方裁判所の指定した弁護士により、政治資金規正法違反(収支報告書の虚偽記載)の事実で東京地裁に起訴された。この起訴は、検察審査会の起訴すべきとの議決(起訴議決)を受けて行われたものである。この事件をめぐってはいろいろな議論がされてきたが、検察審査会はどうして専門家である検察官が二度も不起訴処分にした事件を起訴すべきとしたのか、検察審査会はどういう基準でこういう結論に至ったのか、検察官と検察審査会の判断基準はなぜどのように違っているのかについての議論もそのひとつである。しかし、これまでの議論には混乱もあるように思われる。まずは検察審査会の制度について簡単に触れた上で、この問題について考えてみたい。
2 検察審査会の起訴議決
この事件では、小沢氏の元秘書3名が昨年2月に起訴され、今月7日にその第一回公判が開かれている。小沢氏については市民団体から東京地方検察庁に告発があったが、東京地検は嫌疑不十分として不起訴処分とした。これに対し、告発人から検察審査会に審査の申し立てがあり、昨年4月、検察審査会が起訴を相当とする議決をした。検察審査会とは、衆議院議員の選挙権を有している人たちのなかからくじで選ばれた11人の検察審査員から構成される機関で、各地方裁判所やその支部の所在地に置かれている。検察官が事件を不起訴にした場合、これに不服のある被害者、告訴人、告発人等の申立てを受けて、検察官の処分の当否を審査し、不起訴相当、不起訴不当又は起訴相当の議決をする。前二者の議決は過半数で行われるが、「起訴相当」の議決は8名以上の多数が必要とされる。
検察審査会の議決は検察官を拘束しないが、起訴相当又は不起訴不当の議決があった場合には、検察官は起訴すべきか否か、あるいは、不起訴処分が相当であったかどうかの検討を行わなければならない。東京地検は、小沢氏の事件について起訴相当の議決を受けて再捜査をしたものの、再び嫌疑不十分として不起訴処分にした。
2009年(平成21年)5月までであれば、この段階でこの事件は刑事事件としては収束していたはずである。しかし、2004年(平成16年)に検察審査会法が改正され、新たに41条の2の規定が設けられ、2009年5月21日から施行されていた。この規定は、検察審査会が「起訴相当」と議決した事件について再度不起訴の処分があった場合には、検察審査会はその不起訴処分の当否について審査をし、起訴相当と認めるときは起訴議決をすべきと規定している。起訴議決には8名以上の多数が必要である。そして、起訴議決があったときは、裁判所の指定する弁護士が起訴及びその後の手続を担当する。小沢氏の事件では、検察審査会が、2010年9月に起訴議決をし、10月に議決書を作成して公表した。今回の起訴はこの起訴議決に基づくものである。
3 検察官の起訴の基準
検察官が刑事事件の犯人として人を起訴する場合、その人物がその犯罪を行ったことを検察官が確信していればよいのか(主観的基準)、裁判所が有罪判決をする一定以上の見込みが必要か(客観的基準)、また、それら確信や見込みの程度としてはどの程度のものが必要かという問題は、きわめて重大な問題である。しかし、法律にはこの点に関する基準を定めた規定はない。もっぱら、検察部内の慣行に基づいている。なお、日本国憲法40条は、抑留又は拘禁された後に無罪判決を受けたときは法律の定めるところにより国にその補償を求めることができると定めており(刑事補償法が刑事補償の制度について具体的に規定している。)、検察部内の起訴の基準に関する慣行に大いに関係はあるが、この規定は身柄の拘束の補償について規定したもので、起訴の基準を直接左右するものではない(法律の建前上は、勾留されている被告人が起訴された場合には、一定の除外事由がある場合を除き保釈が認められる。)。
検察実務において、起訴するにはどのような性質のどの程度の確からしさがなければならないとされているかについて、司法研修所(司法試験を合格した裁判官、検察官、弁護士の卵に対して行われる実務教育を担う最高裁所管の研修機関)の検察講義案は、「検察の実務においては、的確な証拠に基づき有罪判決が得られる高度の見込みがある場合に限って起訴するという原則に厳格に従っている」と述べている。しかし、執拗に犯罪事実の自認を求め、有罪率が99.9%以上という捜査や裁判の実情をみるにつけ、実際は、「有罪判決が得られる高度の見込みがある」にとどまらず、大勢としては、より高度の「有罪判決を得られる確実な見込みがある」という基準に基づいているようにも思われる。いずれにしても、こうした保守的な基準に基づく慣行が不文律として存在している。
これに対し、社会が関心を有する事件については、検察官として嫌疑が十分にあると考える以上、実際に有罪判決を得られる確信までなくとも、裁判所の判断を仰ぐという選択肢もあり得るという考え方もあるが、少数派にとどまる。なお、手柄意識・偏見・無知等に起因する根拠のない確信や粗忽・杜撰としか言いようのない捜査に基づく起訴が時としてみられるが、それらは別の問題である。
「有罪判決が得られる高度の見込み」にせよ、「有罪判決を得られる確実な見込み」にせよ、検察実務における基準は、検察官自身の主観ではなく、裁判所の判断をベースにする客観的な基準である。日本の裁判官は、その大多数が最初から職業裁判官の道を歩み、裁判所組織のなかで裁判官に必要な素養を身につけて行くこともあって、裁判官によって判断の基準が大きく異なるということはあまりない。そして、検察官は、日々の実務や上司の決裁、研修その他を通じ、裁判官がどのように証拠を評価し、どのような判断をするかを感覚として身につけて行く。裁判員裁判制度が発足したことにより、裁判員裁判の対象となる重大事件(死刑、無期懲役・禁固に当たる罪、故意に被害者を死亡させた罪)については不確実な要素が加わる兆しもなしとはしないが、少なくとも当分の間はそのことで起訴の慣行が変化することはないだろう。
4 検察審査会の判断基準
これに対し、一般人から選ばれた11人の検察審査員から成る検察審査会はプロではない。したがって、裁判官がどのように証拠を評価し、どのような判断をするかについての具体的知識はない。検察審査会の審査には、必要な場合には弁護士から選ばれた審査補助員がつくが、審査補助員が刑事裁判の実情に精通しているとしても、短時日のうちに素人の検察審査員にプロの感覚を理解させることは難しい。当該事件が起訴された場合の見通しを審査補助員が述べることがあるとしても、検察審査員が良心に従って自ら判断しようとすれば、審査補助員の述べたことは一つの判断材料にしかならないのは当然だろう。そうすると、検察審査員が実際に依拠する基準は、自分が審査対象事件について有罪無罪を判断する場合にはどう判断するだろうかという主観的基準であるか、そうでないとしても、主観的な判断の影響を受けることは当然である。
検察審査員が検察実務の基準をある程度理解し、承認したとしても、実際の証拠関係への基準の適用について、リスク回避的な傾向の強い検察官と必ずしもそうでない検察審査員とで見解を異にすることは大いにあり得る。
加えて、検察実務がどのような基準で運用されているにせよ、その基準は法律上の基準ではないから、検察審査員はこれに拘束されない。ちなみに、日本の検察実務で設定されている起訴のハードルは、アメリカ、イギリス、ドイツなどよりも高い。
このように、検察官の判断と検察審査会の判断とが異なってもおかしくない制度的な理由が存在する。そもそも検察審査会制度の趣旨、特に、平成16年の改正で新設された起訴議決の制度の趣旨は、公訴権の行使に国民の感覚を反映させるという点にあるのだから、法律の素人である検察審査員がプロの常識と異なる社会の常識を検察審査会の場に持ち込むことは、法律上当然のこととして想定されているといえよう。
5 むすび
起訴に当たっての証拠の十分性に関する基準という問題は、これまで議論される機会が少なかった問題であるが、小沢氏についての検察審査会の起訴議決及びその後の起訴によって改めてクローズアップされた。起訴する場合にはどのような性質のどの程度の確からしさがなければならないかという問題は、刑事司法の基本に関わる問題である。そして、検察審査会による起訴議決の制度の運営次第では、これまでの起訴不起訴の決定の基準に何らかの変化が生じる可能性を指摘する声もある。そうした観点から、小沢氏に対する政治資金規正法違反被告事件の推移だけでなく、今後の検察審査会の行動とこれへの検察の対応が注目される。