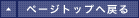2011年4月28日 宮本 英治
1 はじめに
今年4月12日に、労働組合法上の労働者概念に関する2つの最高裁(第3小法廷)判決が言い渡された。会社と業務委託契約を締結してその修理補修等の業務に従事する者、財団と出演契約を締結していた合唱団員について、いずれも、労組法上の労働者として認めたものである。
従来から、管弦楽団員(中日放送管弦楽団事件(注1))やプロ野球選手(注2)のような独立事業者である熟練技能者が労組法上の労働者といえるかどうかが問題になっていたが、近年、会社の従業員が行っていた仕事を外部の個人業者に委託する(アウトソーシング化)事例が増えており、特定企業の一定業務を専属的に処理するこれらの外部受託業者が、労働組合に加入し、団体交渉を求め、これに対して会社が外部受託業者は労組法上の労働者ではないとして、団体交渉を拒否し、争いになる事例が出てきている。
労組法上の労働者は、「職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者(労組法3条)」と定義されており、労働組合を結成して、会社と労働条件その他の待遇等について団体交渉を行うことができるが、実際にどのような場合に労組法上の労働者と認められるのかについては、その判断基準や具体的な適用をめぐって、労働委員会や下級審の判断が分かれていた。上記2つの判決の概要を紹介し、これらの判決の意義及びその及ぼす影響等について、検討していきたい。
2 INAXメンテナンス事件(最三小判 平23.4.12 不当労働行為救済命令取消請求事件)
(1)事案の概要
住宅設備機器の修理補修等を業とするINAXメンテナンス(以下、「会社」)が、会社と業務委託契約を締結してその修理補修業務に従事する者(カスタマーエンジニア、以下「CE」)が加入した労働組合からCEの労働条件の変更等を議題とする団体交渉の申入れを受け、CEは会社の労働者に当たらないとして上記申入れを拒絶した。会社は、大阪府労働委員会から上記申入れに応じないことは不当労働行為に該当するとして団体交渉に応ずべきこと等を命じられ、中央労働委員会(以下、「中労委」)に対し再審査の申立てをしたが、これを棄却するとの命令を受けたため、その取消しを求めて訴訟を提起した。
東京地裁(注3)は、中労委命令を相当とし、会社の請求を棄却したが、東京高裁(注4)は、CEの基本的性格は会社の業務受託者であり、いわゆる外注先とみるのが実体に合致しており、労組法上の労働者に当たるということはできないとして、中労委命令を取り消した。
(2)最高裁判決の要旨
最高裁は、以下の「諸事情を総合考慮すれば、CEは、会社との関係において労働組合法上の労働者に当たると解するのが相当である。」と判示し、原判決(東京高裁判決)を破棄した。
① 修理補修業務を現実に行う可能性がある会社の従業員はごく一部であり、会社は、主として約590名いるCEをライセンス制度等で管理し、担当地域に配置を割り振って日常的な修理補修等の業務に対応させており、その業務日・休日等を指定していたというのであるから、CEは、会社の事業の遂行に不可欠な労働力として、その恒常的な確保のために会社の組織に組み入れられていた。
② 業務委託契約の内容は、会社の定めた覚書によって規律され、会社がCEとの間の契約内容を一方的に決定していた。
③ CEの報酬は、会社が商品や修理内容に従ってあらかじめ決定した顧客等に対する請求金額に、当該CEにつき会社が決定した級ごとに定められた一定率を乗じ、これに時間外手当等に相当する金額を加算する方法で支払われていたのであるから、労務の提供の対価としての性質を有するものである。
④ 会社から修理補修等の依頼を受けた場合、CEは業務を直ちに遂行するものとされ、CEが承諾拒否を行う割合は1%弱であり、業務委託契約の存続期間は1年間で会社に異議があれば更新されないものとされていたこと、各CEの報酬額は会社が毎年決定する級によって差が生じており、その担当地域も会社が決定していたこと等に照らし、各当事者の認識や契約の実際の運用においては、CEは、基本的に会社による個別の修理補修等の依頼に応ずべき関係にあった。
⑤ CEは、原則として業務日の午前8時半から午後7時までは会社から発注連絡を受けることになっていた上、業務を行う際、会社の制服の着用、その名刺の携行、業務終了時の報告書の会社への送付が求められ、会社の定めた各種マニュアルに基づく業務の遂行を求められていたというのであるから、CEは、会社の指定する業務遂行方法に従い、その指揮監督の下に労務の提供を行っており、かつ、その業務について場所的にも時間的にも一定の拘束を受けていた。
なお、原審は、CEは独自に営業活動を行って収益を上げることも認められていたともいうが、平均的なCEにとって独自の営業活動を行う時間的余裕は乏しかったものと推認され、CEが自ら営業主体となって修理補修を行っていた例はほとんどなかったことがうかがわれるのであって、そのような例外的事象を重視することは相当とはいえない。
3 新国立劇場運営財団事件(最三小判 平23.4.12 不当労働行為救済命令取消請求事件)
(1)事案の概要
年間を通して多数のオペラ公演を主催している新国立劇場運営財団(以下、「財団」)が、毎年実施する合唱団員選抜の手続において、音楽家等の個人加盟による職能別労働組合に加入している合唱団員1名(以下、「A」)を不合格とし、Aの不合格に関する組合からの団体交渉の申入れに応じなかった(財団は、過去4年間は、Aを原則として年間シーズンの全ての公演に出演することが可能である契約メンバーの合唱団員として合格とし、Aとの間で期間1年の出演基本契約を締結していた。)。財団は、東京都労働委員会から、財団が上記申入れに応じなかったことは不当労働行為に該当するとして団体交渉に応ずべきこと等を命じられ、中労委に対し再審査の申立をしたが、これを棄却する旨の命令を受けたため、その取消しを求めて訴訟を提起した。(なお、組合は、財団がAを不合格としたこと自体も不当労働行為に当たるとして救済を求め、本件の裁判の審理の対象となっているが、この点については本レポートでは割愛する。)
東京地裁(注5)、東京高裁(注6)とも、契約メンバーは、仕事の依頼等の諾否の自由があり、労務ないし業務の処分について財団から指揮命令、支配監督を受ける関係になっているとは認められず、契約メンバーであるAは労組法上の労働者に当たるということはできないとした。
(2)最高裁判決の要旨
最高裁は、以下の「諸事情を総合考慮すれば、契約メンバーであるAは、財団との関係において労働組合法上の労働者に当たると解するのが相当である。」と判示し、原判決(東京高裁判決)を破棄し、原審に差し戻した。
① 出演基本契約は、オペラ公演を主催する財団が、一定水準以上の者を原則として年間シーズンの全ての公演に出演することが可能である契約メンバーとして確保することにより、上記各公演を円滑かつ確実に遂行することを目的として締結されていたものであるといえるから、契約メンバーは、上記各公演の実施に不可欠な歌唱労働力として財団の組織に組み入れられていた。
② 契約メンバーは、出演基本契約を締結する際、財団から、全ての個別公演に出演するために可能な限りの調整をすることを要望されており、出演基本契約書の別紙には、年間シーズンの公演名、公演時期、上演回数及び当該契約メンバーの出演の有無等が記載されていたことなどに照らせば、契約メンバーが何らの理由もなく全く自由に公演を辞退することができたものということはできず、むしろ、契約メンバーが個別公演への出演を辞退した例は、出産、育児や他の公演への出演等を理由とする僅少なものにとどまっていたことにも鑑みると、各当事者の認識や契約の実際の運用においては、契約メンバーは、基本的に財団からの個別公演出演の申込みに応ずべき関係にあった。
③ 出演基本契約の内容は、財団により一方的に決定され、契約メンバーがいかなる態様で歌唱の労務を提供するかについても、専ら財団が、一方的に決定していた。
④ 契約メンバーは、財団により決定された公演日程等に従い、各個別公演及びその稽古につき、その指定する演目に応じて歌唱の労務を提供していたのであり、歌唱技能の提供の方法や提供すべき歌唱の内容については財団の選定する合唱指揮者等の指揮を受け、稽古への参加状況については財団の監督を受けていたというのであるから、契約メンバーは、財団の指揮監督の下において歌唱の労務を提供していた。公演や稽古の日時、場所等は、専ら財団が一方的に決定しており、Aが公演への出演等のため新国立劇場に行った日数は、1シーズンに約230日であったというのであるから、契約メンバーは時間的にも場所的にも一定の拘束を受けていた。
⑤ 契約メンバーは、歌唱の労務を提供した場合に、所定の単価及び計算方法に基づいて算定された報酬の支払を受け、超過稽古手当も支払われており、その報酬は、歌唱の労務の提供それ自体の対価である。
4 上記2つの判決の意義及びその影響について
(1)労組法上の労働者を判断する上で、総合考慮すべき諸事情(判断要素)を示したこと
上記3の新国立劇場運営財団事件の判決が合唱団員を労組法上の労働者として認めたことは、管弦楽団員の労働者性を認めた昭和51年の中日放送管弦楽団事件の判決(注1)に沿ったものといえる。しかし、最高裁は、中日放送管弦楽団事件において、労組法上の労働者について定義しておらず、判断要素も明確でなかったことから、その後の労働委員会や下級審の判断が分かれていた。本件の2つの判決において、最高裁は、労組法上の労働者の定義は示さなかったが、以下の諸事情(判断要素)を総合考慮した。
① 事業の遂行に不可欠な労働力として、会社の組織に組み入れられていたか。
② 契約内容を会社が一方的に決めていたか。
③ 基本的に会社による業務ないし労務の提供の依頼に応ずべき関係にあったか。
④ 報酬は、労務の対価としての性質を有するものであるか。
⑤ 会社の指揮監督下に労務を提供しており、時間的にも場所的にも拘束を受けていたか。
上記諸事情(判断要素)は、多くの学説が提唱し(注7)、中労委が考慮した判断要素(注8)と大きく異なるものではない。他方、本件2つの判決は、「諸事情を総合考慮すれば」と述べるにとどまり、上記の判断要素は、労働者性の一般的基準とまでされていない。会社としては、労組法上の労働者と認められるかどうか判断するに際して、本件2つの判決の示した諸事情(判断要素)に該当する事実関係を調査・検討する必要がある。そして、調査・検討した諸事情を総合考慮することになるが、各判断要素の重要性も定かではないので、会社にとって、労組法上の労働者に該当するかどうか予測することは、容易ではないと思われる。
(2)労組法上の労働者に当たるかどうかは、契約の形式面ではなく、労働供給関係の実態に基づいて判断すること
労組法上の労働者性の判断要素たる諸事情を総合考慮する上で、業務委託契約、基本契約といった契約の形式面を重視するのか、労務供給関係の実態に即して判断するのかの問題がある。上記2のINAXメンテナンス事件の原審(注4)では、個別業務はこれを拒絶することが認められているなど業務の依頼に対して諾否の自由がある(上記(1)の判断要素③)、業務を実際にいついかなる方法で行うかについては全面的にその裁量に委ねられているなど、業務の遂行に当たり時間的場所的拘束を受けず、会社から具体的な指揮監督を受けることがない、独自に営業活動を行って収益を上げることも認められていた(上記(1)の判断要素⑤)など最高裁と正反対の事実認定を行い、労組法上の労働者に該当しないとした。上記3の新国立劇場運営財団事件の原審(注6)も、個別公演出演契約の締結が法的な義務として合意されておらず、諾否の自由がある(上記(1)の判断要素③)、オペラ公演のもつ集団的舞台芸術性に由来する諸制約が課せられるということ以外には、法的な指揮命令ないし支配監督関係の成立を差し挟む余地がない(上記(1)の判断要素⑤)などと認定している。これらの原審判決は、業務委託契約や基本契約などの契約の形式面を重視し、このような判断に至った。これに対し、最高裁は、各当事者の認識や契約の実際の運用においては、基本的には会社(財団)からの依頼(申込み)に応ずべき関係にあった(上記(1)の判断要素③)、「平均的なCEにとって独自の営業活動を行う時間的余裕は乏しかったと推認され、CEが自ら営業主体となって修理補修を行っていた例はほとんどなかったことがうかがわれる(上記(1)の判断要素⑤)。」と判示しており、業務委託契約や基本契約を形式的に解釈するのではなく、労務供給関係の実態に即して労働者性を判断している。このように実態面を重視することにより、今後は、従来よりも広く労組法上の労働者性が認められる方向になるであろう。
(3)上記2のINAXメンテナンス事件の判決は、外部受託業者を労組法上の労働者として認めた最初の最高裁判決であること
今まで、外部受託業者を労組法上の労働者として認めた最高裁判決はなかった。高裁レベルでは、上記2のINAXメンテナンス事件の原審が労働者性を否定しているほか、ビクターサービスエンジニアリング事件(注9、上告中)においても、修理業務に従事する個人のサービス代行店の労働者性を否定していたことから、外部受託業者を労組法上の労働者として認めた上記2のINAXメンテナンス事件の判決の影響は大きいと思われる。会社としては、外部受託業者の組合から団体交渉を求められた場合、労働契約を締結していないということのみを理由として、団体交渉を拒否するのではなく、より慎重に対応することが必要になってくる。
外部受託業者が労組法上の労働者にあたるかどうかは、上記の判断要素を総合考慮して判断することになるが、外部受託といっても、その契約形態や労働供給関係の実態は様々であり、個別の事例ごとに判断していく必要がある。上記2のINAXメンテナンス事件の判決では、田原裁判官は、「CE制度の求める業務以外に主たる業務を行っていたり、・・・複数の有資格者を雇用し複数の直轄営業所やサービスセンターを担当しているような場合には、・・・純然たる業務委託契約であって、一般の外注契約関係と異ならないものといえよう。」と補足意見を述べているが、このような場合は、外部受託業者の労組法上の労働者性は否定されることになるであろう。
(4)労組法上の労働者の概念と労働契約法、労働基準法上の労働者の概念とは異なること
本件2つの判決では、外部受託業者と合唱団員が、労組法上の労働者と認められたが、労働契約法や労働基準法上の労働者として認められたわけではない。
労組法上の労働者は、労働契約法や労基法上の労働者とは異なると一般には解されている。最高裁も、上記3の新国立劇場運営財団事件で合唱団員Aを労組法上の労働者と認めながら、Aの別訴の労働契約上の権利を有する地位確認等請求については、認めていない(労働契約関係を認めることができないとした東京高裁判決(注10)に対しAが上告したが、平成21年3月27日上告棄却、上告不受理決定が下された。)。また、プロ野球選手は、個人事業主であり、労基法上の労働者ではないと解されるが、労組法上の労働者である(注2)。このように労組法上の労働者と労基法上の労働者の概念は異なっており、労組法上の労働者として認められたからといって、労働契約法や労基法上の労働時間、賃金、休暇、解雇等の規定が適用されるわけではない。したがって、労働契約、業務委託契約のいずれの契約形態によるかの違いは、依然存在することになる。ただ、外部受託業者であっても、労働契約とほとんど変わらないほど使用従属関係が強いものは、労基法の労働者として認められる可能性がある。
5 おわりに
本件の2つの最高裁判決において、労組法上の労働者を判断する際に総合考慮する諸事情(判断要素)が示され、契約を形式的に解釈するのではなく、労働供給関係の実態に即して判断する必要があることが明らかにされた。また、外部受託業者であっても、労組法上の労働者と認められる場合があることが明らかになった。会社としては、外部受託業者等の組合から団体交渉を求められた場合、労働契約を締結していないということのみを理由として、団体交渉を拒否するのではなく、より慎重に対応することが必要になってくる。ただ、労働供給関係の実態に即して諸事情(判断要素)を総合考慮するということは、個別事案ごとに諸事情に該当する事実関係を調査・検討し、判断する必要があるということであり、会社にとって、労組法上の労働者に該当するかどうか予測することは、容易ではないだろう。
以上
*****************************************************************************
【注1】中日放送管弦楽団事件 最一小判 昭51.5.6 民集30巻4号437頁
【注2】プロ野球選手会は、労働組合として都労委から資格認定を受けており、裁判所も労働組合として団体交渉権を有することを前提として審理を行っている(東京高決平16.9.8 労判879号90頁)
【注3】INAXメンテナンス事件-東京地判 平21.4.22 労判982号17頁
【注4】INAXメンテナンス事件-東京高判 平21.9.16 労判989号12頁
【注5】新国立劇場運営財団事件-東京地判 平20.7.31 労判967号5頁
【注6】新国立劇場運営財団事件-東京高判 平21.3.25 労判981号13頁
【注7】菅野和夫「労働法(第9版)」(弘文堂、2010年)514~515頁
【注8】中労委命令平成19.10.3労経速1987号12頁
【注9】ビクターサービスエンジニアリング事件 東京高判平22.8.26 労経速2083号23頁(上告中)
【注10】新国立劇場運営財団事件(地位確認等請求事件)東京高判 平19.5.16.労判944号52頁